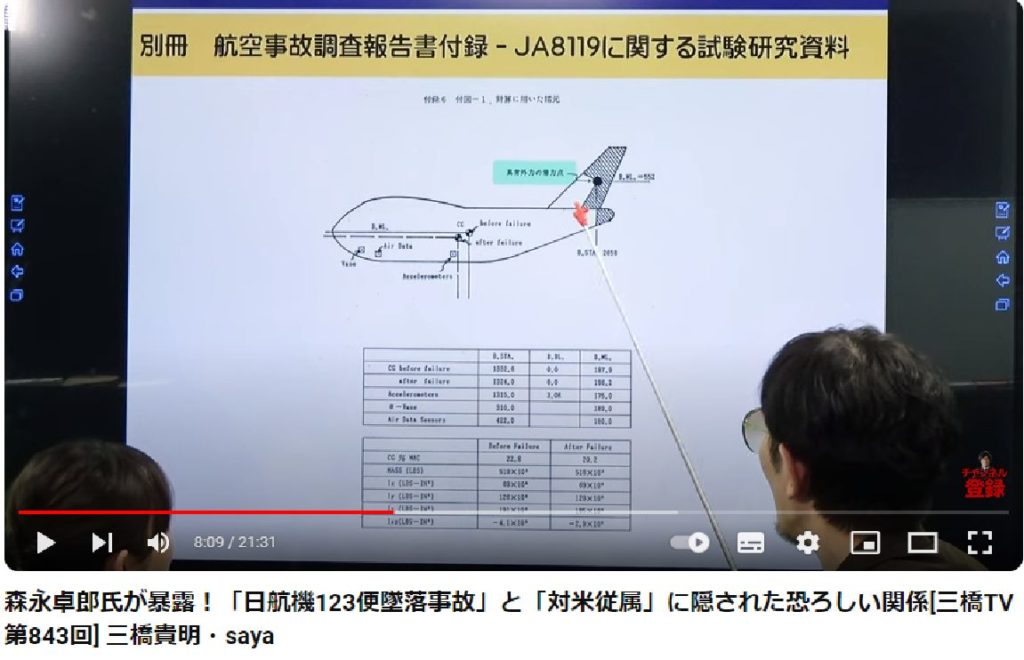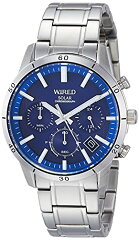武蔵国二宮 金鑚神社は、伝説によると、日本武尊(ヤマトタケルのみこと)が蝦夷討伐の際に立ち寄り、火打石を身代わりとして安置して 天照大御神 と 須佐之男命 を祭ったということです。文献上には 貞観4年862年で、正六位上神階にある「金佐奈神」官社に列したといい、神階は同年に従五位下です。
この神社は人々がおがむ拝殿はありますが、本殿がありません。
神社には普通は本殿があるものですが、こちらでは裏の山、御室山をご神体としています。
この様に山などをご神体としていて本殿がないのは、奈良の大神神社、諏訪の諏訪大社のみと
言われています。このことを考えると、この神社がヤマトタケルが立ち寄ったと云う時代とも重なります。
現在の建物がいつ建てられたかは、調べることが出来ませんでした。
ただし、地元の豪族の阿保氏が1500年頃に多宝塔を寄進したことが明らかで、拝殿などはこの頃以降の建物ではないかと推測しました。

駐車場に止めて歩くとすぐにこの巨木がありました。

深い森林があります。写真で解りにくいかもですが、ななり奥まで見えています。

1500年頃、地元の有力氏である阿保氏が神社に寄進しました。一階は四角形ですが、二階が円形になっています。この一部円形の建物というのは、国内ではめずらしいのではないでしょうか?阿保という苗字は、現在も地元の字の地名として残っています。 この建造物は、細かい芸術品の様な作りをしていて、私が思うにこれを現在作れば、功名な宮大工に頼むことになるし、材料をここまで運ぶのの一苦労で、百億円単位のお金が掛かるのではないでしょうか?

巨木

双子の巨木

境内に続く道。まだまだ遠い。

道すがら、ジャングルのようなうっそうとした森のかげ。ここも奥行きがかなりあります。

規模感が解りにくいかもですが、車と比べると木々の大きさが解ります。

五月の新緑が美しい。

多宝塔へ続く道と、多宝塔へ上る石の階段。

多宝塔。二階部分が円形。

石垣があった。ここは戦国時代は山の城があった。多分、お城の石垣。

新緑の風景。

奥にあるのが礼拝する場所。手前に石造りの塀があった。

拝殿の手前の大木。

三つ葉葵か?将軍家からの寄進か?

拝殿の隅にでっぱった木がある。これは構造上、何の意味もないので、装飾の為に故意に作られた。

拝殿の北側の壁。ここから先はご神体エリアのため、立ち入り禁止。

拝殿の東隣の建物の屋根に目が行く。何かと豪華な装飾が目立つ。

屋根のでっぱりの端部は銅吹きの装飾が施されていて、柄は日本伝統の「青海波」の紋様である。

拝殿の屋根も豪華な作り。装飾が重ねられた屋根。ゴールドに光るのは金箔だろうか?

小さい建物の角の部分。ここを見ると、この時代の建物がどの様な構造で作られていたか解りやすい。

小さい建物の屋根の構造が内側から見て取れる。切妻っぽい造りに見える。

屋根は銅吹きに見える。そして、いわゆる鼻と言われる横に並んでいる木はわずかにそっているように見える。全部を同じそり具合に揃えるのはかなりの手間だな。

横に綱が張ってある。ある種の結界を表している。神社自体が結界の中なのですけど。横に張った綱。横綱。相撲の横綱は現人神(あらひとがみ)であり、横綱のしこは、大地の神を慰撫する霊力がある。

参拝する場所の遠景。この奥の山がご神体=本殿。

案内図。

かなさな川とかなさな橋。

名前の解らない草花。昭和天皇が喜びそうな花。

石碑。沢山句碑があった。

石碑。句碑。親鸞という文字があった。

美しい五月の新緑。まるで糸魚川の翡翠かエメラルドのよう。

山=本殿 急斜面になっている。少数だが鹿が棲んでいるいるという話。

小物の灯籠。どのような構造になっているのか、明瞭に解る。支えの梁が45度の角度で張り出している。

これ、大きな石です。石一個、軽く10万円は超える値段でしょう。大きいんです。これがコンクリートだったら、安かったでしょうけどね。動かないように隣同士がくっつくように削ってますね。私が訪問した時も約10組ほどの参拝者が来ていました。車がある人は関東なら割とアクセスしやすいかもです。ヤマトタケルの尊もここを通って蝦夷の地へ向かいましたから。