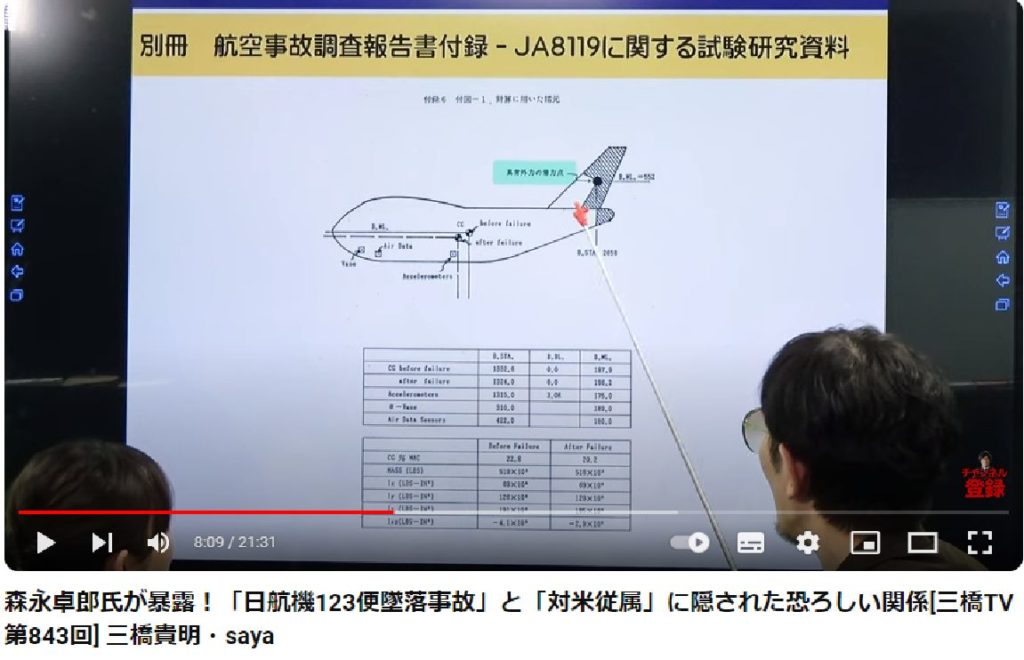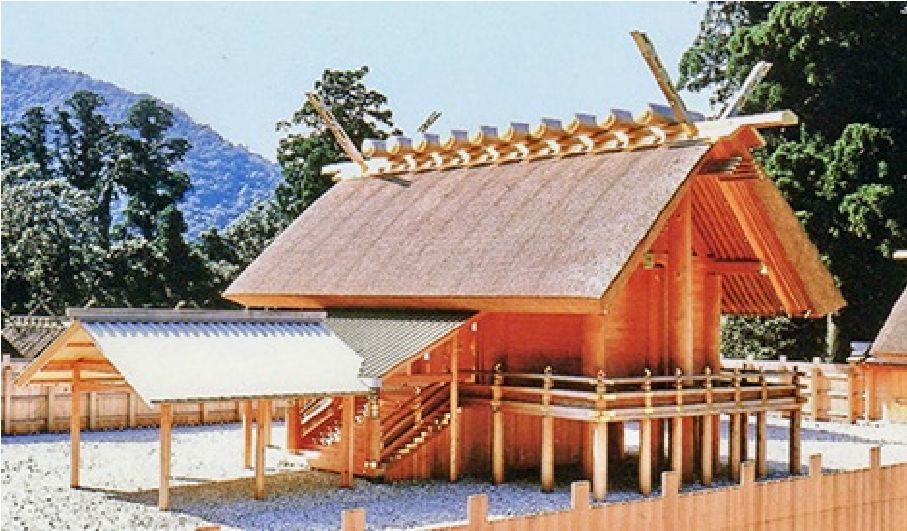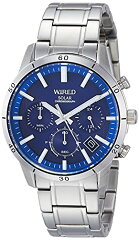(原文)
さまことなる山の姿の、紺青(こんじょう)を塗りたるやうなるに、
雪の消ゆる世もなくつもりたれば、色濃き衣(きぬ)に、白き衵(あこめ)着たらむやうに見えて、
山のいただきのすこし平らぎたるより、煙は立ち上る。
夕暮は火の燃えたつも見ゆ。
(現代語訳)
世間並でない山の姿の、紺青の色を塗ったようであるところに、
雪が消える間もなくつもっているので、色の濃い衣に、白い衵を着ているように見えて、
山の頂が少し平になっている所から、煙が立ち上っている。
夕暮は火が燃え建つのも見える。
この文章は平安朝に書かれた「更級日記」の一節で、主人公の娘が父の赴任地の千葉県から、京へ移る移動の際に直接、目にしたことです。
この文章を読んで、みなさんはどう思いますか?
私は怖くて、恐怖を覚えますよ。
大きな大きな富士山が、もくもくと煙を出しているのですよ。
そして、夕暮れには火が見えるって!?
怖くないですか?
調べて見ましたら、平安時代は富士山が大小含めて何十回も噴火していた時代だったとのことです。
そんなに頻繁に噴火していたなら、この少女は人からその話は既に聞いていて、「ああ、これか」と思った位なんでしょう。
でも、現代人にとっては、怖いですよ。
今、富士山でなくても、夜に噴火の火が見える山って、桜島位しか思いつかないですからね。
調べたら、地質的にはまだまだ若い火山なんだそうです。
10万年前~1万年位前まで、また1万年前~2千年前位で区分されているようです。