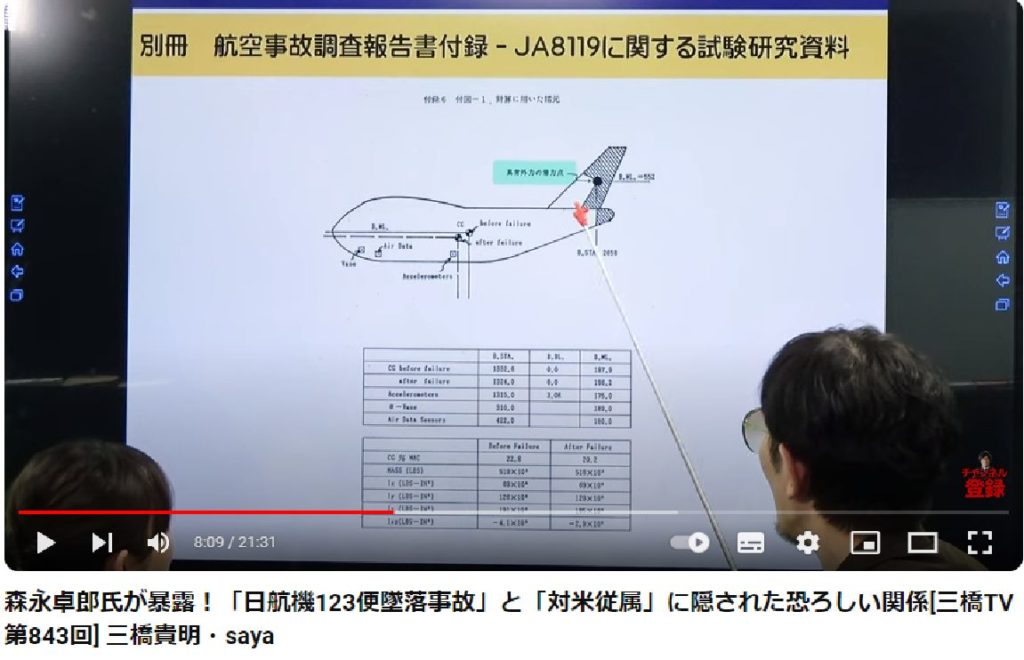| 投稿者:ジュリア 投稿日:2021年 9月 1日(水)13時01分42秒 日本人は最低賃金を抑え込む事の弊害を知らない 労働者を買い叩き続ける限りデフレは終わらない 岩崎 博充 : 経済ジャーナリスト 最低賃金の引き上げ額が過去最大になるというニュースが注目されている。 正式には、9月になってから各都道府県の労働局長が最終決定するもようだが、平均で「時給930円」が最低賃金になる予定だ。 最低賃金については、これまでもさまざまな議論があり、日本の最低賃金はメキシコと同レベルだと報道されるなど、水準の低さが批判されている。 政権が支持基盤である経済界に遠慮して最低賃金を上げることを躊躇しているのではないか、といった声も聞こえてくる。 その一方で、「雇用を守るのか、賃金を上げるのか」といった二者択一を迫る最低賃金引き上げ反対の声も数多く聞こえる。 最低賃金を大幅に上げることの是非や意味、最低賃金と景気の関係はどうなっているのだろうか。 「骨太の方針」で決まった「最低賃金1000円以上」? 最低賃金については、東洋経済オンラインの著者でもあるデービッド・アトキンソン氏などが中心になって、日本の最低賃金の低さの弊害について指摘している。 実際のところ、「賃金の中央値・平均値と最低賃金の比率」を見てみると、日本はOECD(経済協力開発機構)の中でも、29カ国中25位(2018年)でメキシコやチェコと並んで下から3番目の低さになっている(東洋経済オンライン「日本の最低賃金『メキシコ並み』OECD25位の衝撃」、2020年7月23日配信)。 メキシコといえば、国民の40%が貧困層に陥ったという報道があったが、見方によっては一般の平均賃金に比べて、日本の最低賃金が際立って低いことを証明しているデータとも言える。 それだけ、貧富の格差が大きく、最低賃金で暮らし続ける労働者、たとえば非正規労働者などの生活が、いかに苦しいものかを物語る数字といえる。 ちなみに、これを単純に「時給のドルベースの平均値」というデータで見てみると次のようになる。 OECD加盟国の「最低時給額、2020年」(資料:OECD)。 ・オーストラリア…… 12.9ドル ・ルクセンブルク…… 12.6ドル ・フランス…… 12.2ドル ・ドイツ…… 12.0ドル ・ニュージーランド…… 11.8ドル (中略) ・スロベニア…… 8.4ドル ・日本…… 8.2ドル ・ポーランド…… 8.00ドル ・アメリカ……7.3ドル たとえば、サラリーマンのランチ代の平均値を国際比較してみると、日本の賃金の低さが見えてくる。 テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」によると、日本のサラリーマンのランチ代の平均値は649円(新生銀行調べ)。 これがニューヨークでは15ドル(約1650円)、中国の上海では60元(約1020円)だそうだ。 そもそも日本の最低賃金は、日本の国際競争力の低下と連動するかのようになかなか上昇してこなかった。 いまや欧州諸国の7割程度と低く抑えられており、かつては「生活保護世帯」の収入よりも、最低賃金で働く労働者の賃金のほうが低いと就職氷河期世代の悲哀とともに語られた。 景気が悪いときは「最低賃金」を上げるのが経済の常識? なぜ、日本の最低賃金は長期にわたって低迷を続けたのか……。 正規雇用の首を切って、非正規雇用が街にあふれたあたりから、企業側の経営者団体などはさかんに最低賃金の上昇に対して異を唱えるようになった。 政府側もまた、そうした経営者団体の意をくむように低く抑え続けてきた、といってもいいのかもしれない。 しかし、そんな流れを一変させたのが、新型コロナによるパンデミックだ。 日本では、コロナ禍の影響を受けて、全国の最低賃金の目安を決める厚生労働省の諮問機関である「中央最低賃金審議会」が、2020年に関しては最低賃金の引き上げを行うことなく、答申を出さなかった。 その結果、2020年の最低賃金は1円だけ上昇することになった。 コロナ禍であえぐ飲食店や小売業といった業種において雇用を守るには、最低賃金の引き上げなどとんでもない、という論理に労働組合側も納得したからだ。 ところが、欧米主要国は「こんなときこそ最低賃金を引き上げるべき」として、最低賃金を引き上げてきた。 コロナ収束を待たずに、最低賃金の引き上げに積極的に動くドイツのような国も現れた。 実際のケースを紹介しよう(厚生労働省資料より、為替レートは8月24日現在)。 ・イギリス……2021年4月実施、8.72ポンド→8.91ポンド(約1338円、上昇率は2.2%) ・ドイツ……2021年1月以降4段階に分けて最低賃金を引き上げ。 2020年1月実施=9.50ユーロ(約1222円)、上昇率1.6%。 2021年7月実施=9.60ユーロ(約1235円)、上昇率1.1%。 2022年1月実施予定=9.82ユーロ(1263円)、上昇率2.3%。 2022年7月実施予定=10.45ユーロ(約1344円)、上昇率6.4%。 (2021年4月から2年間で11.8%引き上げることが決まっている) ・フランス……2020年1月=10.15ユーロ(1306円)、上昇率1.2%、 2021年1月=10.25ユーロ(約1318円)、上昇率0.99% ・ アメリカ……連邦最低賃金を2009年7月以来の7.25ドルから15ドルへ引上げ予定。約1650円の時給となる予定 アメリカの最低賃金は、これまで極めて低く抑えられてきており、平均賃金の中央値に対する最低賃金のレベルは、OECDの中でも最下位の29位となっている。ところが、そのアメリカもバイデン大統領が最低賃金を時給15ドルに引き上げを目指すと宣言した。 最低賃金が低く抑えられたままでは、さまざまな弊害があると海外では指摘されている。 最低賃金が低いということは「労働分配率」が下落することを意味している。 労働分配率の低下は、以下のような弊害をもたらすとされる。 ① 労働生産性の低迷 ② 所得格差の拡大 ③ 産業構造の転換を遅らせる ④ 技術革新のスピードを鈍化させる 要するに、賃金が低いままでは消費(需要)が伸び悩み、労働生産性が上がらない。 賃金の低迷が、労働者の転職意欲を削いでしまい、産業構造の転換やイノベーションを遅らせてしまう。 労働分配率は、労働者に対して適正な賃金が支払われているかどうかの指標だ。 日本の労働分配率はじりじりと下落しており、資本金10億円以上の大企業では、2009年のピーク時には64.8%(財務省「法人企業統計調査年報」、以下同)だったのが、2018年には51.3%にまで下落。 資本金1000万円未満の小規模企業でも、2009年の89.3%から下落を続け、2018年には78.5%になっている。 役員報酬の高額賃金をカットしてでも、従業員の給与や最低賃金を上昇させて、優秀な人材を確保しなければならないことに、残念ながら日本の経営者は気がついていない。 労働分配率低下の対処法は? 実際に、労働分配率低下への対処法として考えられているのは、次のような「3点セット」だと言われる(「労働分配率の低下をどう見るか~国際比較からのアプローチとわが国への示唆~、日本総研Viewpoint?2018年12月14日より)。 1. 持続的な賃上げ 2. 円滑な労働移転 3. 能力開発支援 こうした対処法で成功したのが、スウェーデンなど北欧諸国といっていいのかもしれない。 日本の菅政権も、遅ればせながらこうした先進国の行動や考え方に呼応する形で最低賃金1000円以上を「骨太の方針」で示したわけだ。 ちなみに、これまでの日本の最低賃金は、「時間額」に変更された2002年度から見てみると、その低迷ぶりがよくわかる。 2002年度は全国平均で663円(厚生労働省「年度別最低賃金額答申状況」より、以下同)。 その後わずかな上昇を続け、2019年度になって27円上昇。 2020年度は新型コロナウイルスの影響でわずか1円の上昇となった。 仮に、2021年度が目安どおりに引き上げられれば28円の上昇となり、2002年から2019年にかけて、最低賃金額は267円上昇したことになる。 日本の消費者物価の上昇と比べれば、最低賃金の上昇も異質ではないのだが、それにしても20年近くかけて300円にも満たない上昇というのは国際的に見て異例と言っていい。 日本が長い間、デフレ経済に陥ってきたことはよく知られている。 最低賃金を含めた収入が抑えられたために、消費が伸びずに景気も回復せず、ひいては転職もできずに生産性も上がらない。 新しい技術革新や構造改革もできない……。 まさに、負の連鎖といっていい。 かつて、韓国が大幅に最低賃金を上昇させたことがあるが、日本ではその政策が「失敗」したかのように一方的に報道されてしまったのも、最低賃金に対する考え方を迷走させたと言える。 韓国で2018年と2019年にそれぞれ16.4%、10.9%と最低賃金を引き上げたことについて、日本では「韓国経済がボロボロになった」と報道された。 しかし、実際の「実質経済成長率」は、IMFによるとそれぞれ2.9%、2.0%となり、日本の0.6%、0.3%よりも高かった(2021年4月現在)。 最低賃金上昇への懸念とは? こうしたこともあって、日本ではなかなか最低賃金の大幅アップができなかったとも言える。 また、メディアのとらえ方も、「雇用か、賃金か」といった二元論でその是非を判断してしまった部分がある。 実際に、日本では長年にわたって賃金上昇が抑えられてきたわけだが、最低賃金の上昇に対して"懸念"があるのも事実だ。 たとえば、 ① 雇用の減少につながる ② 経営基盤への圧力、企業倒産の急増 ③ 転職が活発となり終身雇用制が崩壊する といった不安だ。 しかし、そうした不安だけで長期にわたって最低賃金が抑え込まれてきた、というのも納得いかない。 最低賃金を低く抑えるということは「労働分配率」が低下することを意味していると前述したが、日本では2000年以降、ほとんどの期間で労働分配率が下落してきた。 唯一、2009年以降の数年間だけ上昇している。 要するに、自民党と公明党が下野して「民主党」が政権を取っていた時期だ。 そもそもマクロ経済的にみると、日本は雇用者に対して総じて冷たい国といっていい。 「雇用者報酬」というデータを見ても、それがよくわかる。 「データブック?国際労働比較?2019(独立行政法人?労働政策研究・研修機構)」をベースに試算すると、日本の「雇用者報酬」は、2005年の258兆円に対して、2017年には275兆円と、12年間で6.58%の伸び率だ。 同様の期間を国際比較してみると、次のようになる(各国通貨ベース、日本とアメリカ以外は2018年)。 ●日本……6.58% ●アメリカ……47.23% ●カナダ……61.61% ●英国……51.81% ●ドイツ……52.26% ●フランス…… 36.32% ●スウェーデン…… 73.94% 日本のわずか6.58%に対して、スウェーデンの73.94%を筆頭に、最低でも30%以上の伸び率になっている。 日本が長期にわたって低迷を続けて雇用者=国民が貧困に陥っていく中で、スウェーデンは雇用者に対してきちんと報酬を支払ってきた。 日本とスウェーデンの大きな差と言っていいだろう。 スウェーデンは、1990年代以降、労働生産性においても、そして実質賃金においても圧倒的にOECDの平均値を上回って成長してきている。 国民にきちんと報酬を支払う国の労働生産性は上昇し、そして国民の生活も豊かになると言っていいのかもしれない。 日本の最低賃金制度は、厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会」が審議して決定する。 詳細な仕組みは省くが、管轄が経済政策とは無縁の厚生労働省であること、そして最低賃金の最終決定者が、やはり経済政策の専門家ではない都道府県の労働局長であることには疑問がある。 さらに、2021年には「最低賃金が過去最高額になる」とする同審議会の答申が発表されるや、日経ビジネスオンライン8月16日発信によると、中小企業によって構成されている全国中小企業団体中央会、日本商工会議所、全国商工会連合会といった団体から、「到底納得できるものではない」と言う声明が出されている。 確かに、コロナ禍の中で集中的に犠牲を強いられている飲食店や小売業者などの現場では、大幅な最低賃金の上昇は死活問題となり、深刻な影響が出ると予想される。 しかし、それでも欧米諸国は、この時期に大幅な最低賃金上昇を打ちだしてきた。 そもそも最低賃金が抑えられてきた原因としては、次のようなファクターが考えられる。 終身雇用制の影響も 1.労働組合の衰退 労働組合の衰退も最低賃金の上昇を阻んでいる。 例えば「労働争議による労働損失日数」というデータを見ると、日本の労働争議がいかに少ないか一目瞭然だ。 日本は労働争議をほとんどしない、といっても過言ではない。 2018年の1年間で、次のような結果となっている(資料出所?データブック 国際労働比較 2019) ・日本……1000日 ・アメリカ…… 282万日 ・イギリス…… 27万日 ・ドイツ…… 57万日 ・フランス…… 103万日(2014年) ・韓国…… 55万日 ・オーストラリア…… 11万日 2.経営判断による最低賃金の意図的な抑制 日本企業は、現在でも終身雇用制にこだわるところが多く、若年層の正社員に対しては数を絞って、単純作業などは正社員ではなく非正規社員に依存する経営方針を固めたため、意図的に最低賃金を低くしていると考えられる。 こうした背景には、雇用する側が強い力を持っていて割安で労働力を調達できる状態がある。 いわゆる「モノプソニー」と呼ばれる状況だが、早い話が小泉政権時代に進められた非正規雇用に対する大幅な規制緩和に由来するものだ。 3.「個人消費の拡大=景気回復」を意図的に避けるため? 最低賃金が上昇すれば、個人消費が拡大し景気が回復する。 景気が回復すれば金利上昇を導き出し、現在政府が抱えている財政赤字の利息負担が拡大する。 そうした状況を意図的に抑えるために、あえて最低賃金制度のあり方を含めて政府が放置してきたと考えることもできる。 たとえば、現在の普通国債残高の累積は2021年度末には、990兆円に達する。 利払い費だけで、同じく2021年度末には8兆5000億円に達する。 現在は、日銀がマイナス金利政策を実施しているために、利払い費はこの程度ですんでいるが、金利が1%上昇しただけで利払い費はあっという間に跳ね上がる。 日本銀行が、簡単に金融緩和策を解除できないのも、この国債費という縛りがあるからだ。 仮に、最低賃金を毎年10%ずつ、3年間で30%上昇させたら、いったいどんなシナリオになるのか。 こればかりは、やってみないとわからないのだが、成功しても、失敗しても、財政的には途方もないリスクといっていいだろう。 放置すれば貧富の格差拡大、経済低迷に 4. 失業率の上昇は社会保障制度の崩壊につながる? 日本と欧米諸国との違いがあるとすれば、人口減少や莫大な財政赤字ぐらいだ。 仮に、最低賃金を短期間で10%前後も上昇させたら、確かに雇用は大きな影響を受け、失業率や企業の倒産件数は上昇するかもしれない。 それでも、欧米諸国は最低賃金上昇を選択したわけだが、日本の場合、2021年6月現在の失業率(2.9%)や完全失業者数(206万人)の水準をはるかに超えるレベルの景気悪化が待っているかもしれない。 一方で、ゾンビ企業をいつまでも退場させないほうがよほど大きな問題を抱えていることになかなか気づいていないという側面もある。 いずれにしても、最低賃金の低迷は「貧富の格差拡大」を招き、貧困層を増やすという負の連鎖を招く。 労働の生産効率を低迷させ、転職を阻み、産業構造の変化や技術革新のスピードを遅らせる。 |
Twitterでフォローしよう
Follow @julious_akisue